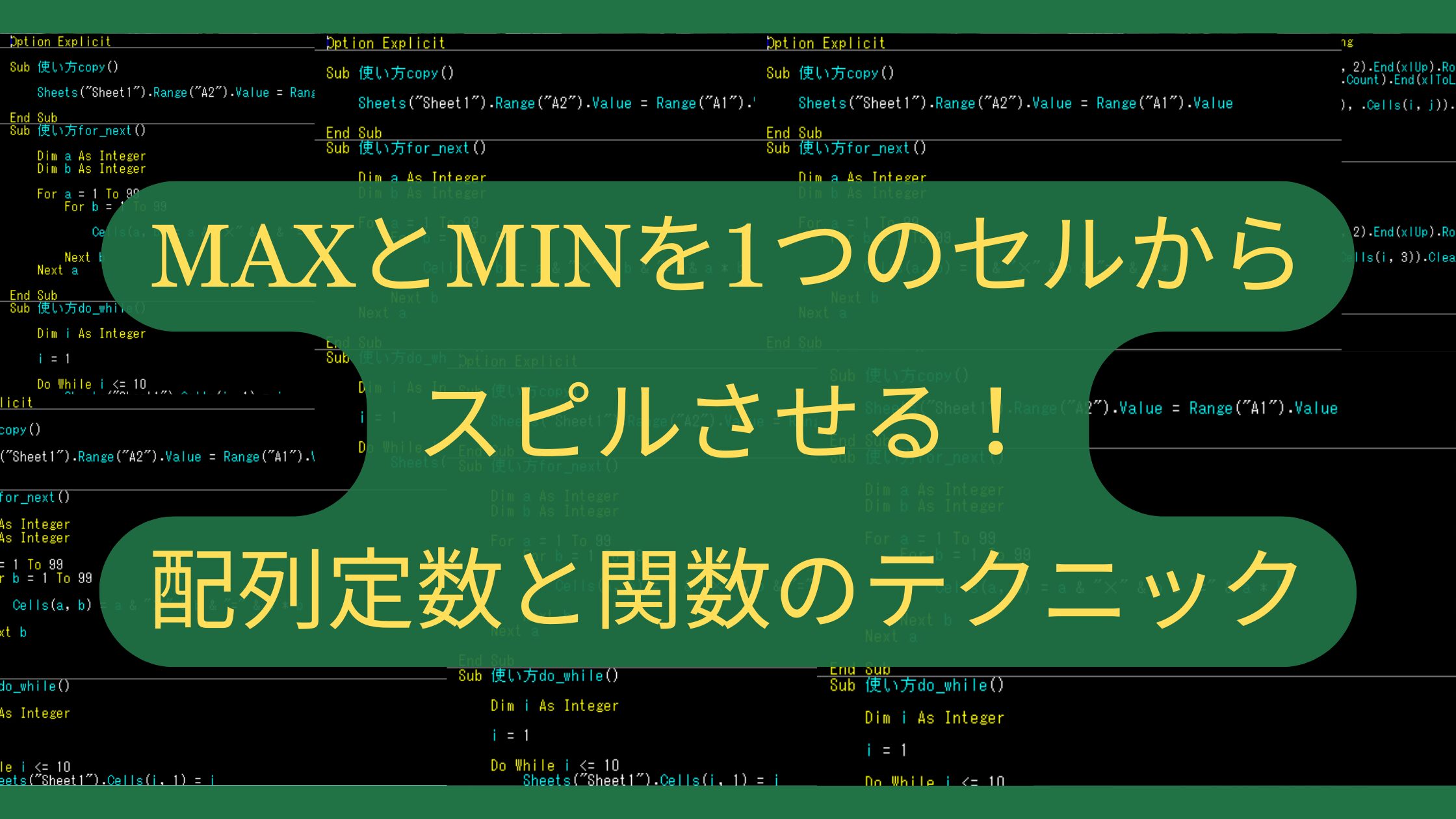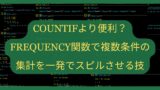- はじめに:MAXとMIN、別々に計算…それで満足ですか?
- 準備:挑戦者となる配列を用意する
- 8つのアプローチで、「最大値&最小値」を同時ゲット!
- まとめ:回り道こそ、最大の近道だ!
はじめに:MAXとMIN、別々に計算…それで満足ですか?
「この範囲の最大値と最小値を知りたい?そんなの、MAX関数とMIN関数で一発でしょ?」
そう思ったあなた、大正解!
通常は、それぞれの関数を別々のセルに入力するのが、最も簡単で分かりやすい方法です。
でも、ちょっと待ってください!
もし、その2つの答え(最大値と最小値)を、一つの数式で2つのセルに同時に表示させたいとしたら…?
「え、そんなことできるの?どうやって1つの数式から2つの答えを…?」
その疑問にお答えするのが、今回の冒険です!
今回は、「最大値と最小値を1つの数式で同時に表示!」という、シンプルながらも配列操作の奥深さを体感できるパズルに、なんと8種類もの異なるアプローチで挑みます。
目的は、
配列定数や特定の関数を使って、複数の結果を同時に返すという、Excelのスピル機能の面白さと、配列の作り方の多様性を学ぶこと!
この冒険が終わる頃には、あなたの「配列脳」が、さらにレベルアップしているかもしれませんよ!
準備:挑戦者となる配列を用意する
本記事では、無料のWeb版Excelを使用して検証および画像の作成を行っています。Windowsはもちろん、MacやLinuxの方もブラウザさえあれば挑戦できます!
何事も、まずは準備から。まっさらなシートのA1セルを起点に、以下の4行4列の数値配列を用意してください。
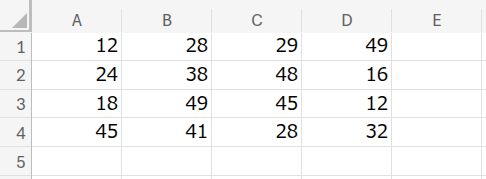
以下の数式をA1セルに貼り付けると表ができますよ!
={12,28,29,49;24,38,48,16;18,49,45,12;45,41,28,32}
この表には、最大値の「49」と最小値の「12」が、あえて複数含まれています。
これも今回のパズルのちょっとしたスパイスです。
私たちのゴールは、この範囲(A1:D4)の中から、最大値「49」と最小値「12」を、一つの数式で、例えばB6セルとB7セルに同時に表示させることです。
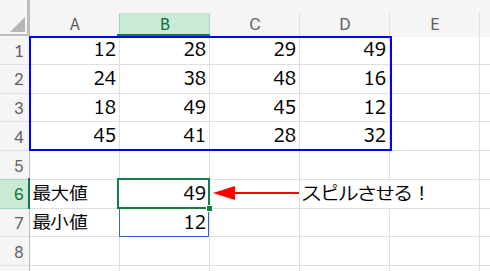
さあ、皆さんならどんな数式を組み立てますか?
「1つの数式で同時に表示させるにはどうしたらいいだろう?」と考えながら読み進めてみてくださいね!
8つのアプローチで、「最大値&最小値」を同時ゲット!
関数の詳細な仕様については、Microsoft公式のヘルプも参考にしてください。
アプローチ1:古典的な配列の合体!(CHOOSE / IF / VSTACK)
考えかた
まず思いつくのは、「最大値を計算する部分」と「最小値を計算する部分」を別々に作り、
最後にそれらを合体させて一つの配列にする、という方法ですね。
数式と解説
=CHOOSE({1;2},MAX(A1:D4),MIN(A1:D4))
・MAX(A1:D4): まず、普通に最大値「49」を計算します。
・MIN(A1:D4): 同じく、最小値「12」を計算します。
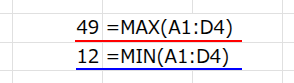
・CHOOSE({1;2}, ..., ...): ここが合体の魔法!CHOOSE関数は、通常CHOOSE(インデックス番号, 値1, 値2, ...)のように使いますが、第1引数に{1;2}という「縦方向の配列定数」を指定すると、「1番目には値1(MAXの結果)を、2番目には値2(MINの結果)を配置した、縦一列の配列を作りなさい」という命令になります。
これにより、{49;12}という配列がスピルして表示されるのです!
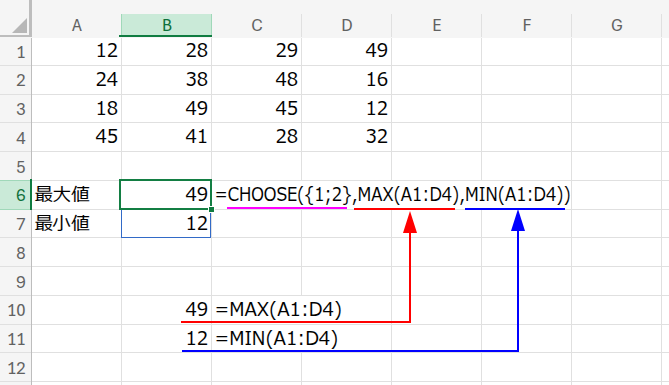
【配列定数の基本】{ }で囲まれた数値や文字列の集まりを配列定数と呼びます。
・カンマ区切り {1,2,3} は横方向(1行)の配列
・セミコロン区切り {1;2;3} は縦方向(1列)の配列
これはExcel配列操作の基本中の基本なので、しっかり覚えておきましょう!
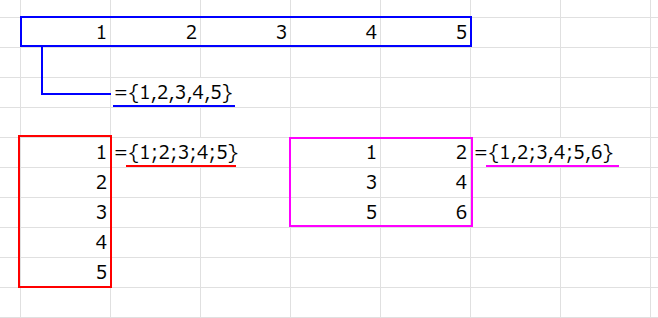
別解
=IF({1;0},MAX(A1:D4),MIN(A1:D4))
IF関数の第1引数に縦配列{1;0}(または{TRUE;FALSE})を入れることでも、同様に結果を分岐させて配列を作れます。
=VSTACK(MAX(A1:D4),MIN(A1:D4))
最新のExcel(Microsoft 365)なら、VSTACK関数で「縦に積む」と命令するのが最もシンプルで分かりやすいですね!
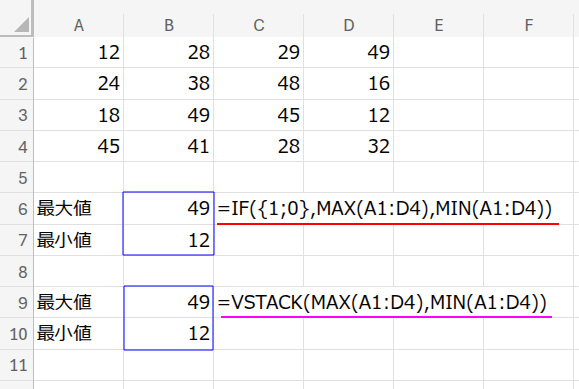
アプローチ2:配列定数の計算マジック
考えかた
次は、配列定数をもっと直接的に計算に組み込む、関数好きにはたまらないテクニックです。
{1;0}と{0;1}という2つのスイッチを使って、1行目ではMAXだけを、2行目ではMINだけを有効にします。
数式と解説
={1;0}*MAX(A1:D4)+{0;1}*MIN(A1:D4)
この数式、一体何が起こっているのでしょうか?
1. {1;0}*MAX(A1:D4): 最大値「49」に、縦配列{1;0}を掛けます。Excelの配列計算(ブロードキャスト)により、結果は{1*49; 0*49}、つまり{49; 0}という配列になります。
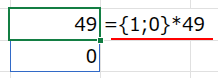
2. {0;1}*MIN(A1:D4): 最小値「12」に、縦配列{0;1}を掛けます。結果は{0*12; 1*12}、つまり{0; 12}という配列になります。
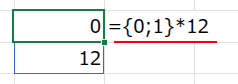
3. {49;0} + {0;12}: 最後に、この2つの配列を足し合わせます。
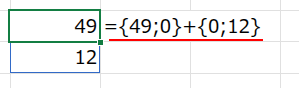
すると、{49+0; 0+12}となり、目的の{49;12}が完成するのです!配列定数は本当に面白いですよね!
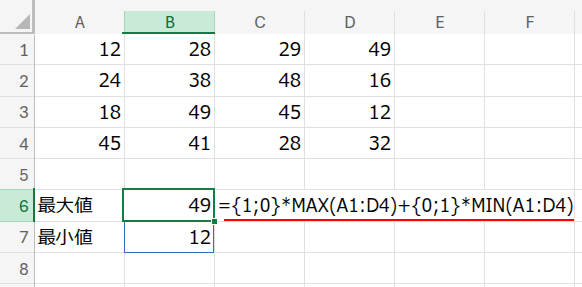
アプローチ3:SUBTOTAL – 関数1つでシンプルに
考えかた
複数の計算を1つの関数で行いたい…そんな時に頼りになるのが、集計の万能選手SUBTOTAL関数です。
第1引数に配列定数を渡すことで、複数の集計結果を同時に得られます。
数式と解説
=SUBTOTAL({4;5},A1:D4)
・{4;5}: SUBTOTAL関数の第1引数「集計方法」には、通常1つの番号を指定しますが、ここに{4;5}という配列定数を指定します。
SUBTOTALでは、「4」がMAX、「5」がMINを意味します。(他にも9=SUM, 1=AVERAGEなどがあります)
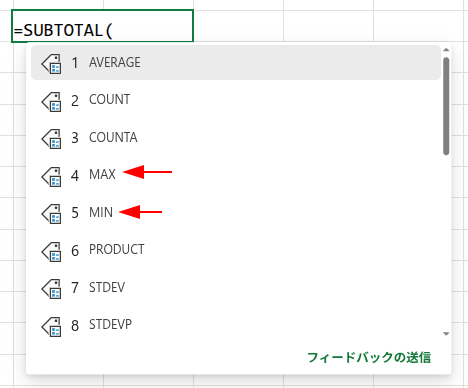
・SUBTOTAL(..., A1:D4): Excelはこれを賢く解釈し、「A1:D4に対して、MAXとMINをそれぞれ計算した結果を配列で返しなさい」と命令されたものとして、{49;12}を返してくれるのです。
おそらくこれが最も短い数式でしょう。
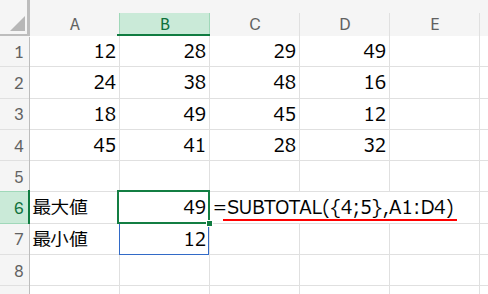
アプローチ4:AGGREGATE – SUBTOTALの強化版
考えかた
SUBTOTALと似た動きをする、さらに高機能なAGGREGATE関数でも同じことができます。
数式と解説
=AGGREGATE({4;5},4,A1:D4)
・{4;5}: AGGREGATE関数の第1引数「集計方法」も、SUBTOTALと同じ番号体系です。
「4」がMAX、「5」がMINです。
・...,4,...: 第2引数「オプション」では、エラー値や非表示行を無視するかなどを指定できます。今回は「4」(何も無視しない)を指定していますが、他のオプションでも動作します。
・AGGREGATE(..., A1:D4): SUBTOTALと同様に、2つの集計結果を配列{49;12}として返します。SUBTOTALより引数は多いですが、より複雑な状況に対応できるのが強みです。
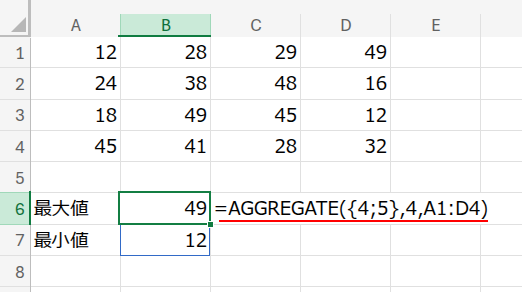
アプローチ5:LARGE – N番目に大きい値
考えかた
「N番目に大きい値」を返すLARGE関数を使ってみましょう。
最大値は「1番目に大きい値」、最小値は「”全部で何個あるか”番目に大きい値」と言い換えられますよね?
数式と解説
=LARGE(A1:D4,(COUNT(A1:D4))^{0;1})
・COUNT(A1:D4): まず、範囲内の数値の個数「16」を計算します。
・(16)^{0;1}: 次に、「16」を{0;1}乗します。数学のルールで、どんな数も0乗すれば「1」、1乗すれば「元の数」になるので、結果は{16^0; 16^1}、つまり{1; 16}という配列になります。
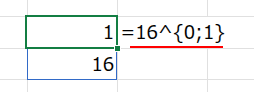
・LARGE(A1:D4,{1;16}): 最後に、LARGE関数に「1番目と16番目に大きい値を配列で返しなさい」と命令し、{49;12}を得ます。
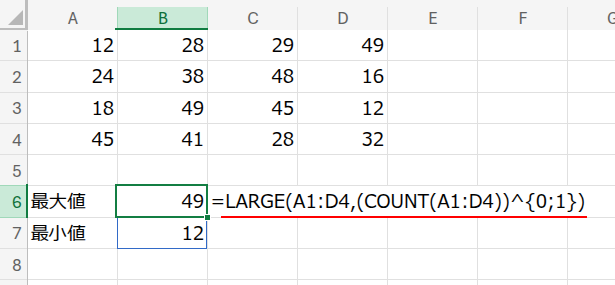
アプローチ6:LARGE + FREQUENCY – 古典的な序列生成
考えかた
アプローチ5と考え方は同じですが、「{1; 個数}」という配列を、最新のべき乗計算ではなく、統計関数FREQUENCYを使った古典的なテクニックで生成します。
数式と解説
=LARGE(A1:D4,FREQUENCY(ROW(INDIRECT("A1:A"&COUNT(A1:D4)+1)),1))
・COUNT(A1:D4)+1: 個数「16」に1を足して「17」を計算します。
・ROW(INDIRECT("A1:A17")): INDIRECT("A1:A17")でA1:A17という参照を作り、その行番号を取得して{1;2;...;17}という連番配列を生成します。
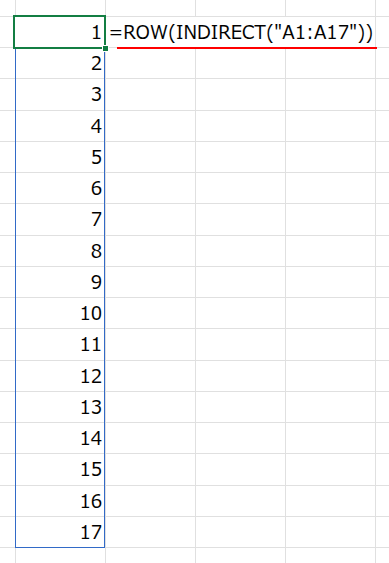
・FREQUENCY(..., 1): FREQUENCY関数はFREQUENCY(データ配列, 区間配列)のように使います。
FREQUENCY関数については以下の記事でも紹介しています!
今回は「データ配列」が{1;...;17}、「区間配列」が「1」です。
FREQUENCYは、データ配列の中から「区間配列の値以下」の個数と、「区間配列の値より大きい」個数を数えます。
つまり、「1以下の個数(=1個)」と「1より大きい個数(=16個)」を数え、{1; 16}という配列を返してくれるのです!
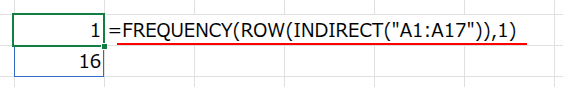
・LARGE(A1:D4,{1;16}): あとはアプローチ5と同じですね。
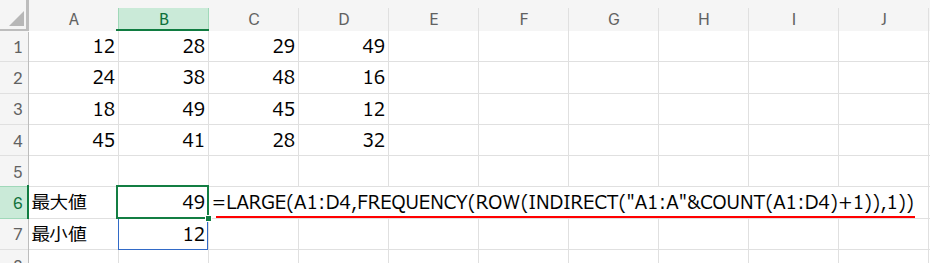
アプローチ7:TAKE + SORT + TOCOL – 最新関数の合わせ技
考えかた
最新の動的配列関数を駆使すれば、こんな簡単な方法もあります。
まず配列を縦一列にして、並び替えてから、最後と最初の値を取り出す、という非常に直感的なロジックです。
数式と解説
=TAKE(SORT(TOCOL(A1:D4)),{-1;1})
・TOCOL(A1:D4): まず、TOCOL関数で4×4の配列を、縦一列16個の数値リストに変換します。
・SORT(...): 次に、SORT関数でこのリストを(デフォルトの)昇順(小さい順)に並び替えます。
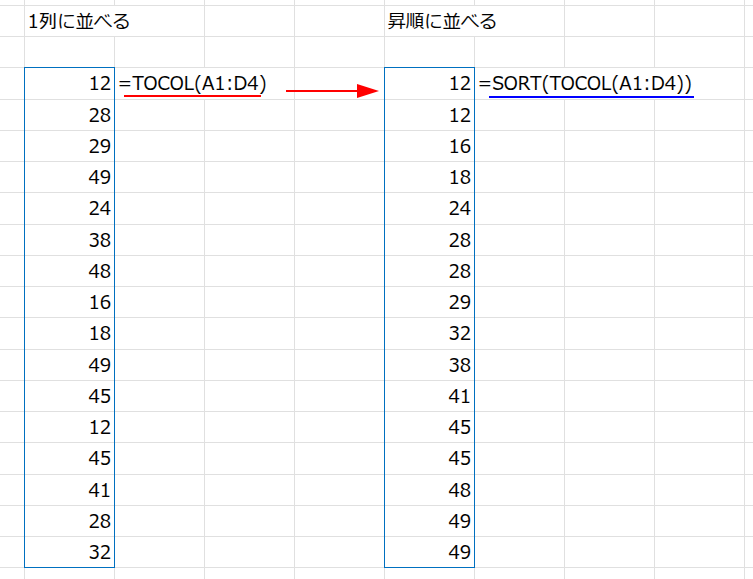
・TAKE(...,{-1;1}): 最後に、TAKE関数が、この昇順リストから「最後の1行(-1)」と「最初の1行」を取り出します。
最後に来るのは最大値、最初に来るのは最小値なので、{49;12}という目的の配列が得られます。
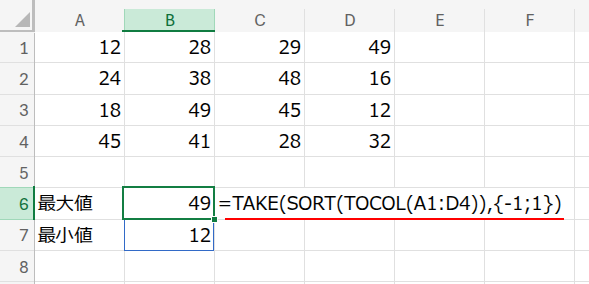
アプローチ8:SUM + COUNTIF – 条件カウントの逆襲
考えかた
これは、完全に「暇つぶし」の領域です(笑)。
COUNTIF関数を使って、「自分より大きい(小さい)数がいくつあるか」を数えることで最大値・最小値を特定し、それをSUM関数で抽出し、配列定数で結合します。
数式と解説
={1;0}*SUM((COUNTIF(A1:D4,">"&A1:D4)=0)*A1:D4)/SUM((COUNTIF(A1:D4,">"&A1:D4)=0)*1)+
{0;1}*SUM((COUNTIF(A1:D4,"<"&A1:D4)=0)*A1:D4)/SUM((COUNTIF(A1:D4,"<"&A1:D4)=0)*1)
この長い数式は、大きく2つのパートに分かれています。
・最大値の特定パート:
1. COUNTIF(A1:D4,">"&A1:D4): 範囲内の各セルに対して、「そのセルの値より大きい値が、範囲内にいくつあるか」を数えます。結果は4×4の配列になります。
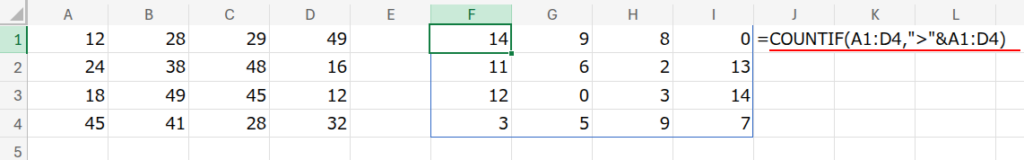
2. ...=0: ステップ1の結果が「0」であるか(=自分より大きい値が存在しないか)を判定します。最大値のセル(今回は2つある49)だけがTRUEになります。
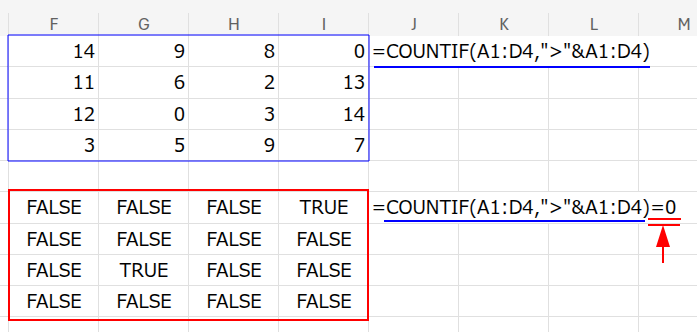
3. (TRUE/FALSE配列)*A1:D4: TRUEの場所(最大値のセル)だけ、元の値が残ります。他は0になります。
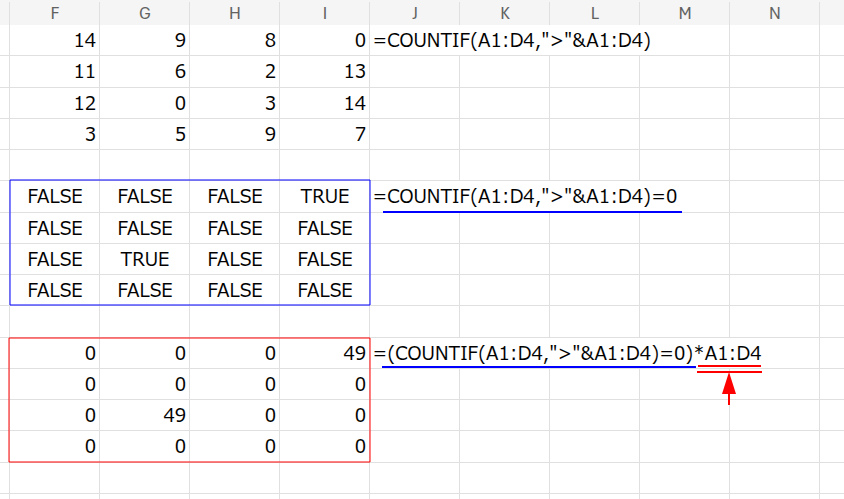
4. SUM(...): 最大値が残った配列を合計します(例: 49+49=98)。
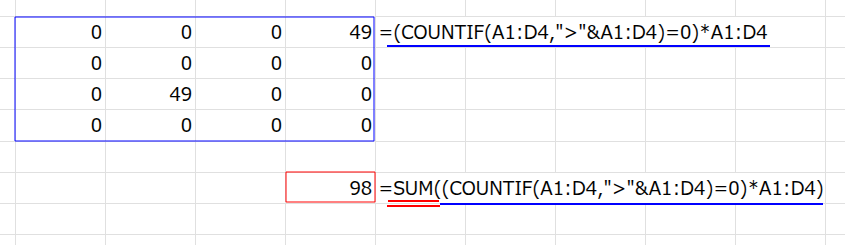
5. SUM((TRUE/FALSE配列)*1): 最大値の個数を数えます(例: 1+1=2)。
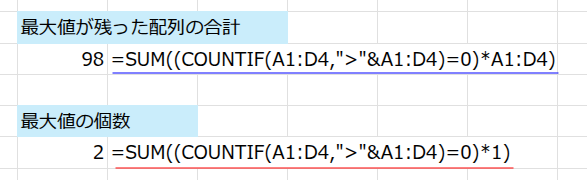
6. (最大値の合計) / (最大値の個数): 合計を個数で割ることで、重複があってもユニークな最大値「49」を計算します。
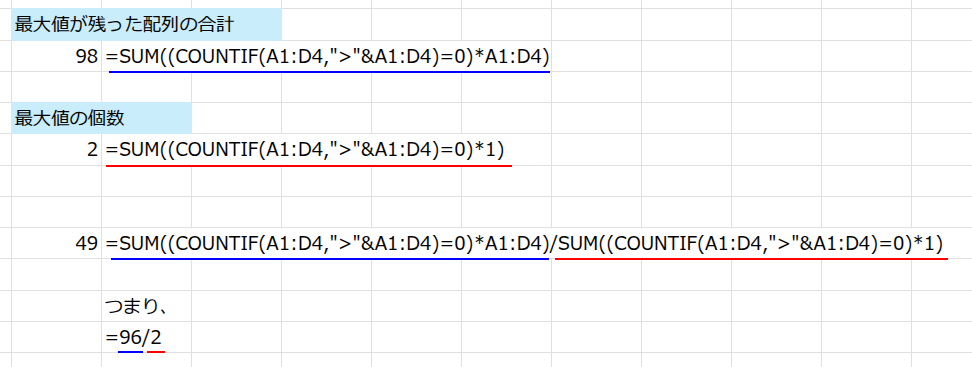
・最小値の特定パート: 同様に、"<"を使って「自分より小さい値が0個」である最小値「12」を計算します。
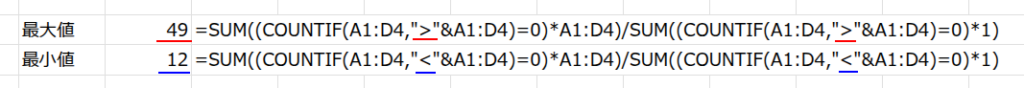
・{1;0}*... + {0;1}*...: 最後に、アプローチ2と同じ配列定数のテクニックで、最大値と最小値を{49;12}という配列に結合します。
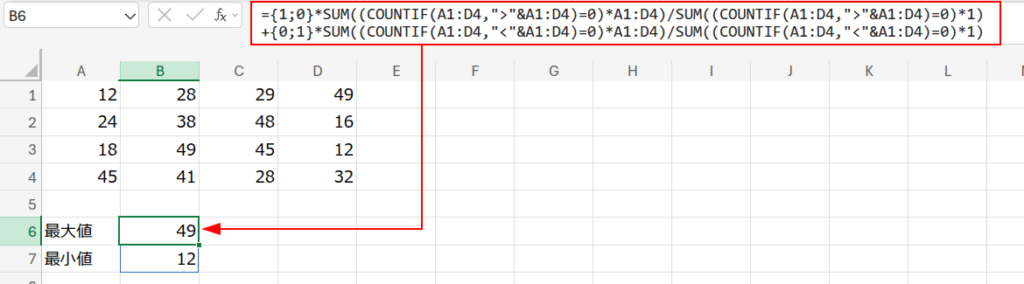
まとめ:回り道こそ、最大の近道だ!
たった一つのシンプルなゴールに対して、これほどまでに多様なアプローチが存在することに、驚かれたのではないでしょうか。
実務で使うなら、正直なところ、それぞれのセルにMAX関数とMIN関数を入力するのが一番分かりやすいでしょう。
どうしても1つの数式で、ということであれば、アプローチ1のCHOOSEやVSTACK、あるいはアプローチ3のSUBTOTALあたりが、比較的読みやすいかもしれません。
しかし、今回挑戦した他の関数パズルたちは、決して無駄ではありません。
配列定数の使い方、動的配列関数の便利さ、そして古い関数の知恵。
これらの知識は、「配列脳」を確実に鍛え、Excelの新しい可能性の扉を開いてくれるはずです。
一見、無駄に見える「回り道」こそが、実は関数の本質的な理解へとつながる、最大の近道なのかもしれません。